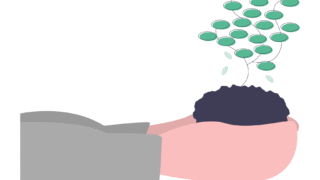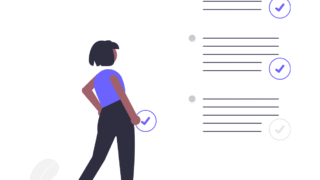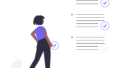この記事では、浪費家から脱却するために、行った資産形成の改善ポイントをひとつずつ紹介します。資産形成に真面目に向き合ってからまだ2年、スタートを切ったばかりです。これからも皆さんといっしょに少しずつ貯金を続けていけたらと思っています。
今日からでも、何かアクション出来そうなことやキッカケがあれば嬉しいなと思います。
まずはお金について知ることからスタート
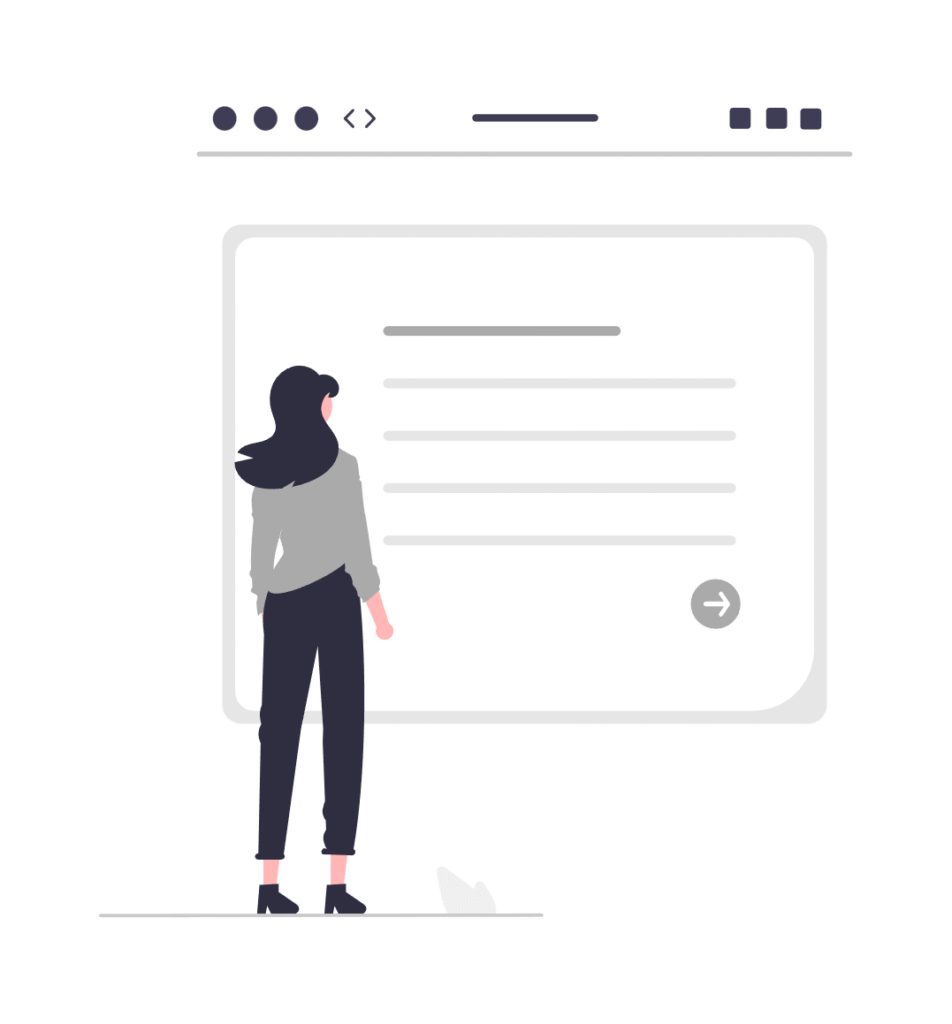
個人的には、「まずは行動から!」というのが好きなのですが、お金に関することは知っておくべきことが多岐に渡るため、まずは「お金について知ること」から始めていきましょう。学習方法については、私がメインで使っていたYouTube学習について、簡単にご紹介します。
YouTubeは使いこなすべし

YouTubeはたくさんのエンタメ動画がありますが、今や人生を変えるレベルの学習ツールでもあるのです。すごい人数のクリエイターがたくさんの有益情報を発信していてくれています。
YouTubeなら主にこんなメリットがありますよ。
- 動画なので、活字のみとは違って、感覚的に勉強を進めることができる。
- 情報発信者が多いため、色々な観点の意見を聞くことができる。
- 無料で視聴することができる。
- 情報の発信が早いため、流行のトピックに関する情報をすぐにピックアップできる。
YouTubeのデメリット:詐欺広告や勧誘には要注意

YouTubeを使って、有力な情報を無料で教授できる時代になりました。ただ、その情報が確かなものか、自分にフィットしているかなど、膨大な量の中から自分に合うコンテンツを選び取る判断力が必要となります。
情報の信憑性を自身で判断しないといけないところが逆にデメリットですね。注意して、チェックしていくことをおすすめします。
おすすめのYouTubeチャンネル

「私ひとりじゃ、自分に合うものなんて分からないよ。何が正解なの?」
「動画ごとに意見が分かれてて、どれを信じればいいの?」
という方もいらっしゃるかもしれません。そこで、私が参考にさせていただき、ぐんぐん知識を吸収させていただいたYouTubeチャンネルをいくつかご紹介します。
- 両学長 リベラルアーツ大学 さん
- 節約オタクふゆこ さん
- 投資うさぎ さん
こちらの3チャンネルは非常にお世話になりました。これらのチャンネルとの出会いが、私の人生の分岐点だったと今では思います。(まだスタートしたばかりですが…)
ご参考まで。
YouTube学習については、こちらの記事にて解説しています。
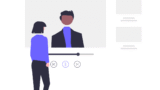
もちろん定番の書籍も
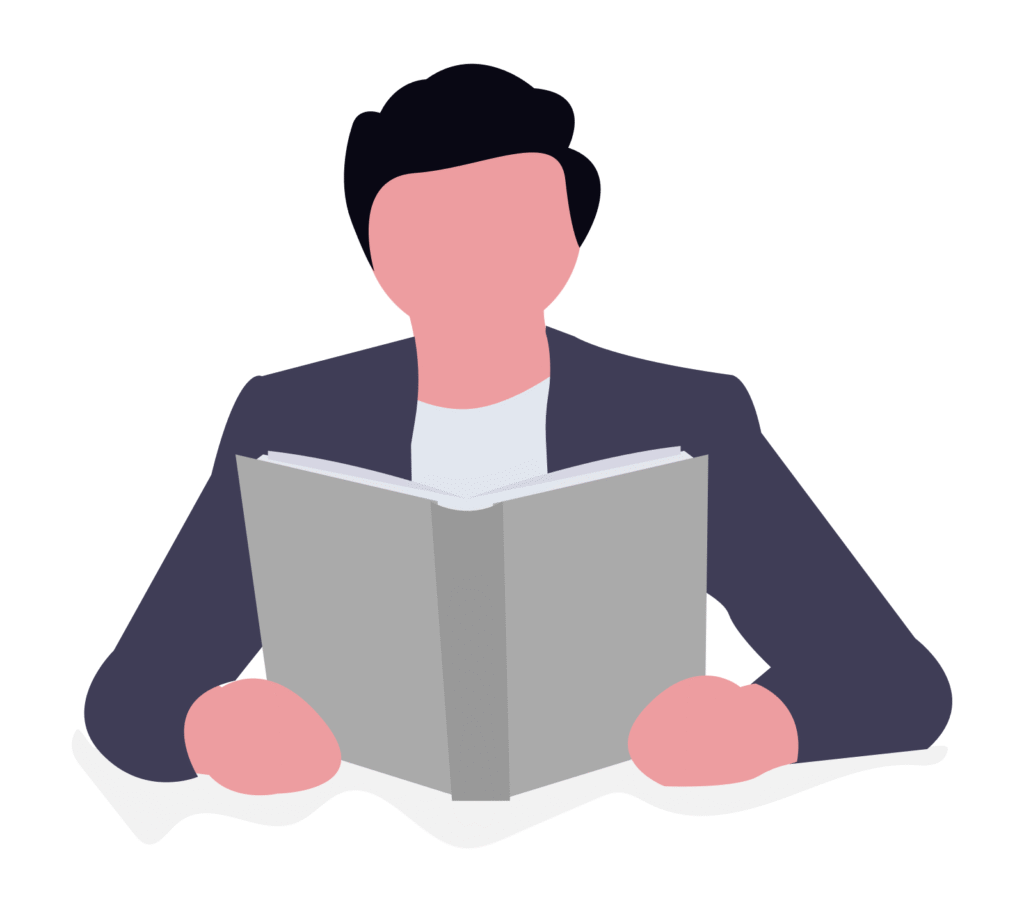
もちろんYouTubeだけではなく、定番であった書籍からもたくさんの情報が得られます。
書籍ならではのメリットもありますね。
- クリエイターの動画よりも、チェックに関わる人数が多いため、書籍の方が信憑性が高い場合が多い
- 紙媒体のため、怪しい広告や勧誘が存在しない
書籍の方が編集者等のチェックが入るため、誤った情報が流れない可能性が高いですよね。
また、詐欺等の怪しい広告や勧誘を避けなければならない動画学習に対し、紙媒体でネットに接続されていない書籍であれば、詐欺の危険性もほぼありません。安心して学習に取り組めますよね。
私が学習のために利用した書籍は、今後に別記事にまとめます。少々お待ちください。
家計管理
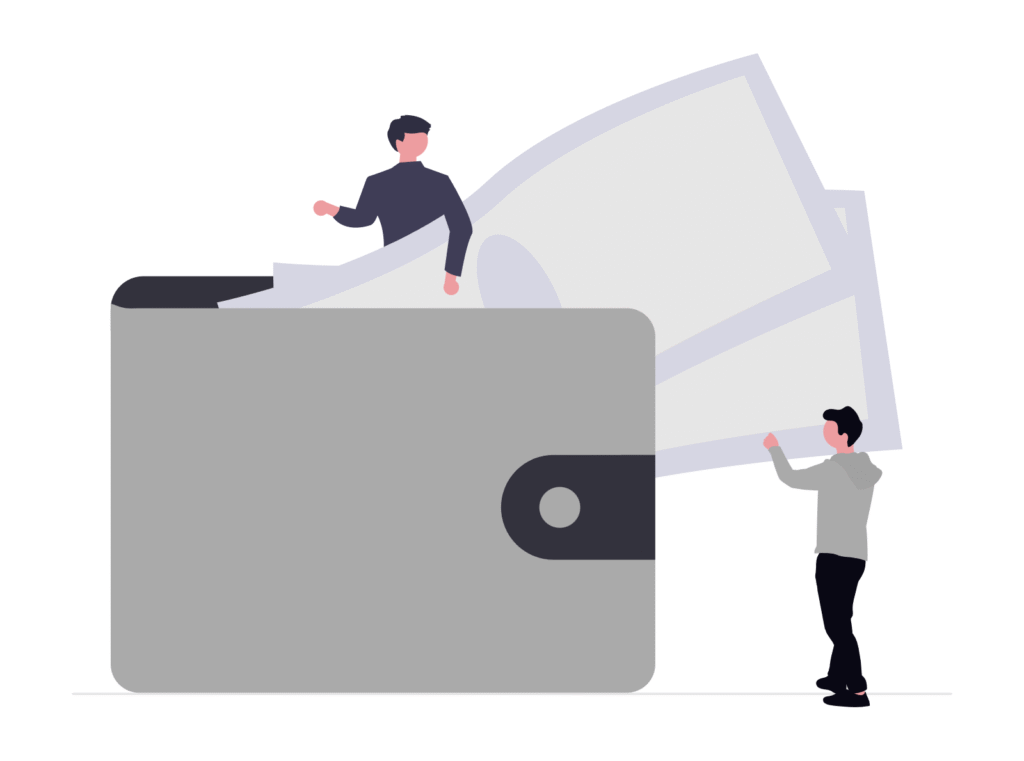
私が実践してきたのは、以下の3点です。
- 書籍(お小遣い帳)
- エクセル
- マネーフォワードME(有料プラン)
私のオススメは、「3.マネーフォワードME(有料プラン)」です。なぜなら、「1.書籍」と「2.エクセル」は手動で作業しなければならないのですが、マネーフォワードMEはほぼ自動で家計簿をつけてくれるからです。
「1.書籍」も「2.エクセル」も含め、順に説明していきますので、何か参考になるものがあれば嬉しいです。
書籍での家計管理
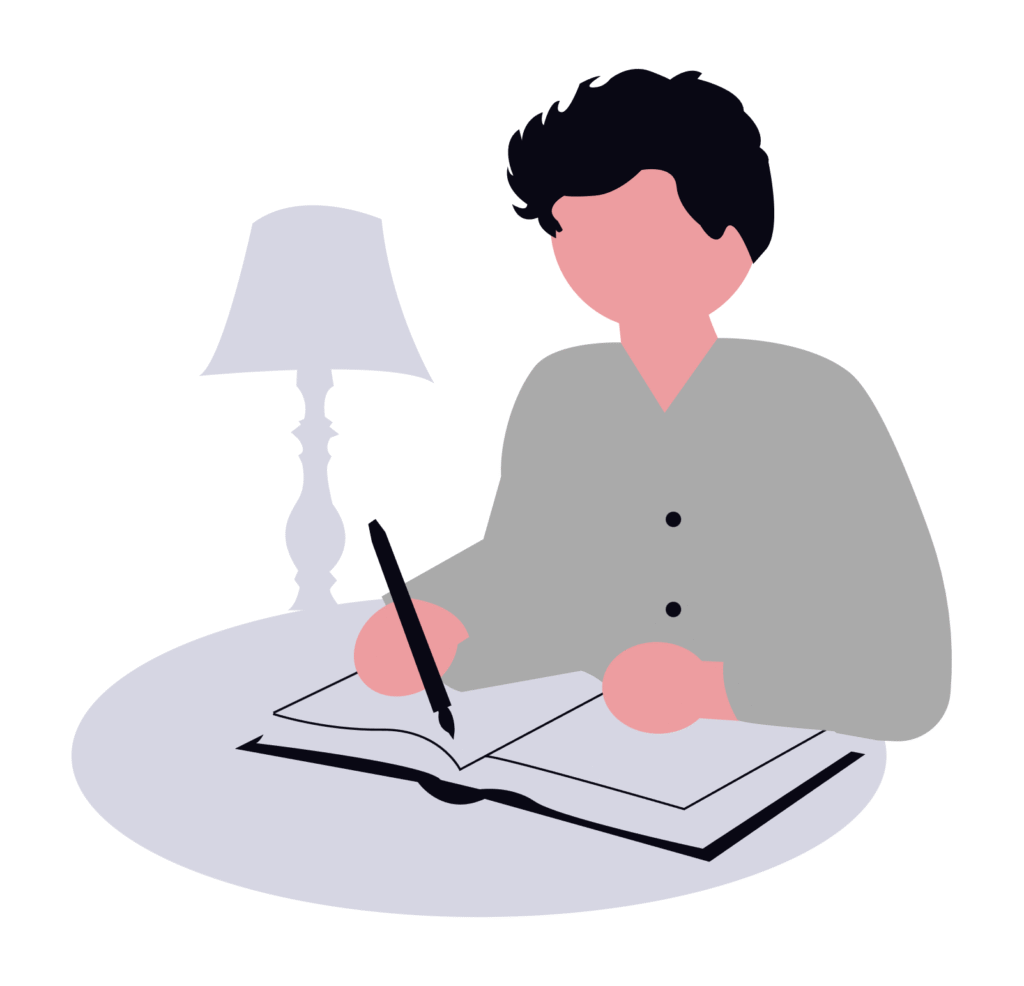
まだ私が独身だった時、マネーリテラシーはどん底でしたが、将来への不安から「家計簿くらいはつけよう」となぜか思い立ち、本屋さんでふと目についたこちらの書籍を購入していました。
カテゴリーが分けられて便利です。直筆で家計簿をつけていくので、何かメモしておきたいことも手軽にできます。
- デジタルはちょっと苦手で、どうしてもアナログなものがいい。
- 家計簿を「手で書く」なら、印象に残りやすい、全体を俯瞰しやすい等のメリットもあります。
当時の私は、後者の感じがあり、どんどん記入して自分のデータが溜まっていくのが心地よかったですね。
エクセルでの家計管理
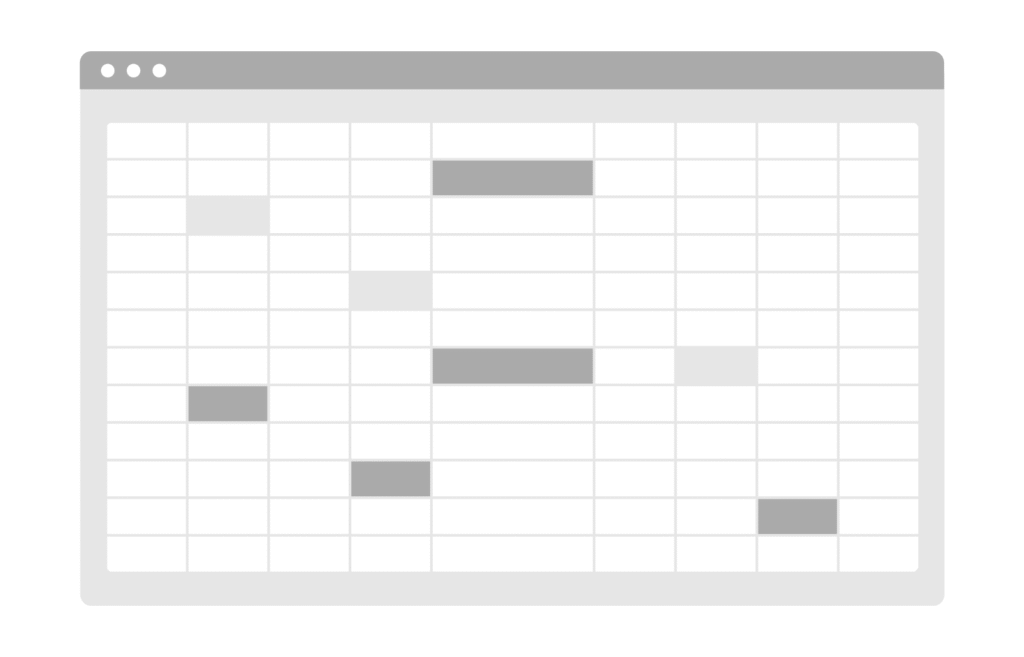
上で紹介した書籍では、1年分でしか記録ができません。
- 1年間継続する習慣をつける。
- どんなジャンルで分けて家計簿をつけるべきかを理解する。
これらを1年間家計簿をつけ終わったところで身につけましたが、次の年分の書籍を買うのは嵩張ってしまうし、お金もかかってしまうなと思い立ちました。
そこで、その書籍のフォーマットをエクセルに転記して、エクセルでの管理を開始しました。下記で書いているアプリ導入までは、この手法を採用していました。
マネーフォワードMEなら自動で家計管理

しかし、手作業で家計簿を更新していくには、少々時間が必要でした。現金利用やカードを利用をメモしておいて、後でまとめて記入していく流れにしていました。特に問題なのが、仕事やプライベートでPCを操作するまとまった時間が取れないと、この家計簿を更新する作業が滞ってしまう点です。
その問題を解決するのは、マネーフォワードMEと有料プランでした。
マネーフォワードMEの有料プランは、登録した銀行口座、クレジットカードなどの情報を自動で読み取り、勝手に記録を進めてくれる家計簿アプリです。マネーフォワードMEの詳細については、こちらの記事で解説しています。
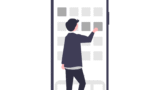
私が実践している家計管理の内訳
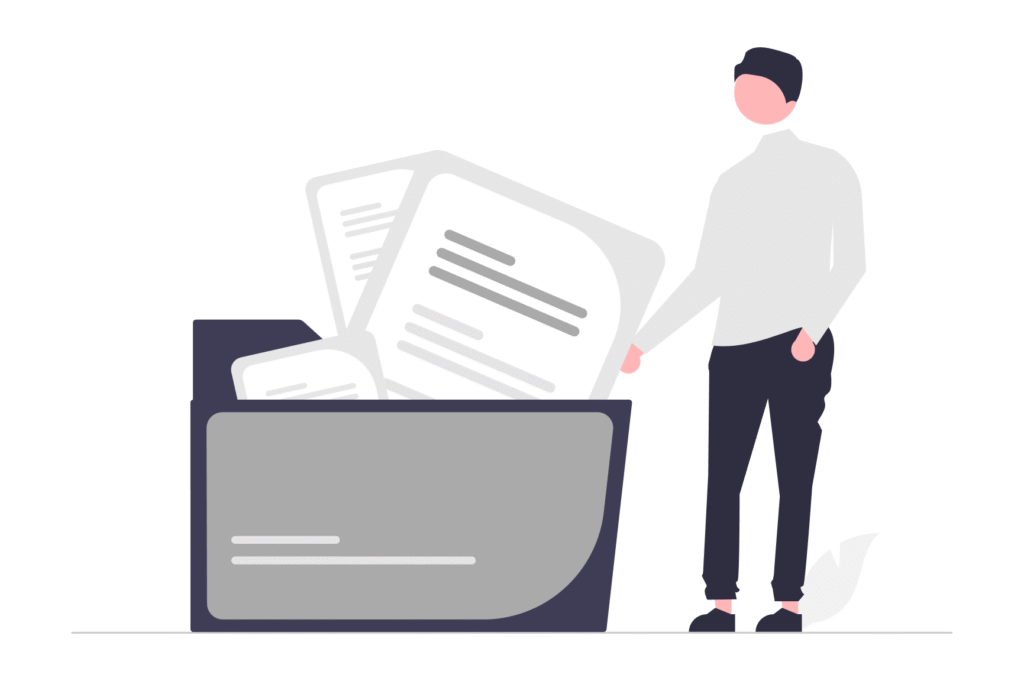
私は、マネーフォワードMEの有料プランを活用し、以下のように4つのグループに分けて管理をしています。
- 月間固定費(月単位の固定的な出費):(例)家賃、光熱費、通信費、SIM利用料、お小遣い
- 月間変動費(月単位の変動的な出費):(例)食費、日用品、医療費
- 年間固定費(年単位の固定的な出費):(例)自動車税、車検
- 年間変動費(年単位の変動的な出費):(例)旅行代、冠婚葬祭、家具家電の買換
この4つのグループ分けについては、こちらの記事で解説しています。

生活防衛費をつくる(現金貯金)
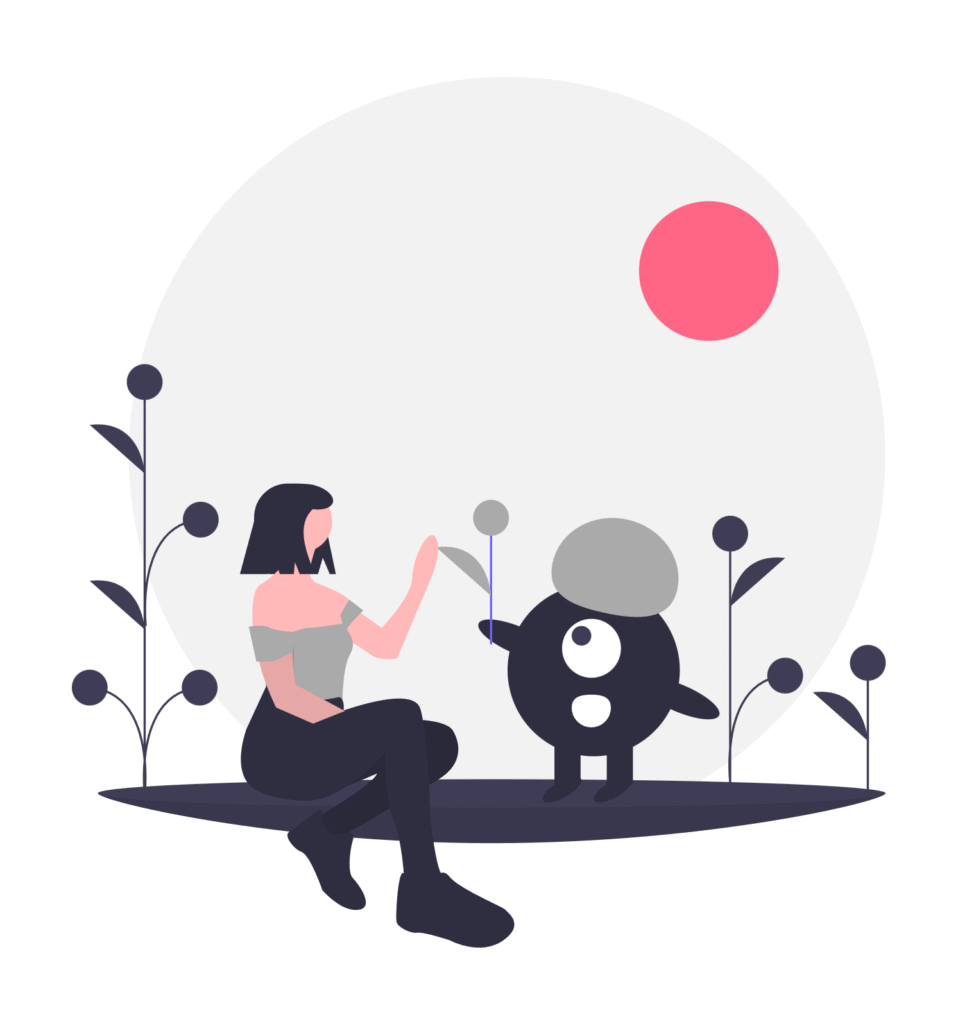
まずは、生活防衛費を現金で確保しておかないといけません。ビジネスパーソンの方々は、今は月々にお給料が出ていると思いますが、突然の失業(①会社都合、②体調やメンタルの不調 など)があった場合に安定的な収入が得られなくなってしまう場合もあります。
そうすると、復職するまでに3~6ヶ月ほど、もし健康やメンタル面の不調で長引いてしまう場合だと、6~12ヶ月ほどかかってしまう場合もあります。その期間中にも最低限の生活ができるように、ミニマムの生活費の6~12ヶ月分を現金で保有しておく必要があります。
固定費の改善
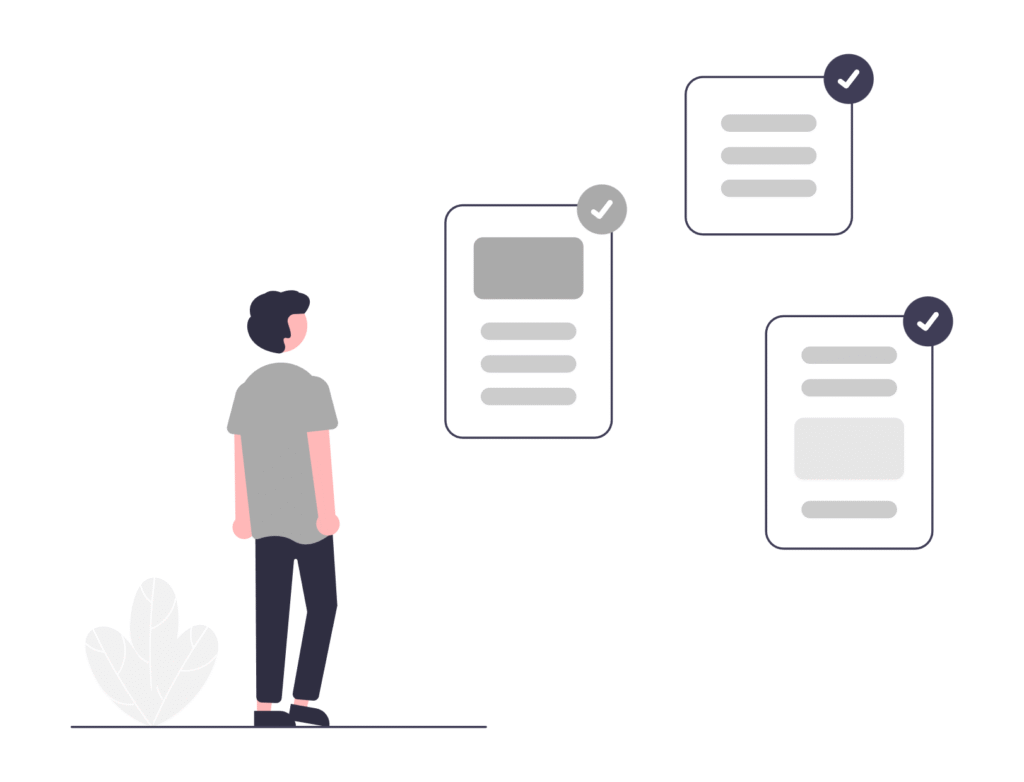
4つのカテゴリーで分けていくと、固定費(月間固定費・年間固定費)について、改善できそうなものが見えてきます。固定費は変動費とは異なり、決まった額になりやすいですよね。実際のところは、光熱費も変動費とも言えますが…。私の場合は、最高額でこの程度だなと把握し、その最高額を固定費の予算として考えています。電気代ですと、大体6,000~11,000円くらいですので、大体10,000円程度として予算を組んでいます。
固定費を改善すると、毎月かかるお金が節約できるので、毎月毎月のお金を節約することができます。しかも一度改善してしまえば、後は放置していても、その効果をずっと受け続けることができるのです。タイムパフォーマンス的にも、優先度を上げて積極的に実施することをオススメします。
固定費を節約すると考えると、我慢しなければならないというイメージが先行すると思います。私が固定費の改善で大事にしていたことは、満足度を下げない=無駄を省く、ことを意識していました。
固定費の改善については、こちらの記事にて解説しています。

変動費の改善

手書き、エクセル、マネーフォワードME等で家計管理ができたら、どの項目にどのくらいの予算が必要かが見えてくると思います。そうすれば、月単位や年単位で変動する出費も読めてくると思います。そうすれば、あとは生活しながら修正していけばOKです。
変動費の予算が決まってしまえば、予算の範囲では自由に使うことができます。節約しなきゃ…と思って不必要に我慢することはありません。
我慢や制限がないとなると、計画的に節約しつつも何にも縛られないため、気持ちよく清々しくお金を使うことができます!そうなる項目をどんどん増やして、我慢はせず、でもどんどんお金が貯まっていくという習慣を構築しちゃいましょう。
こちらの記事も併せてご一読いただければ。

投資で効率よく増やす

お金を増やす手段は色々あると思いますが、まずは「投資≠ギャンブル」ということを早めに分かっておくと、蓄財は本当に有利です。
過去の私もずっとそう思っていましたので、よく分かります。なので、納得できるように投資について勉強をすると、納得して投資を利用した蓄財ができるようになります。
自分で納得できないと、自分の資産を市場に晒し続けることは難しくなってしまいます。不安を煽るような情報に影響されてしまい、途中で投資を止めてしまう結果となってしまいます。
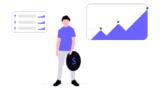
蓄財は自分のペースで
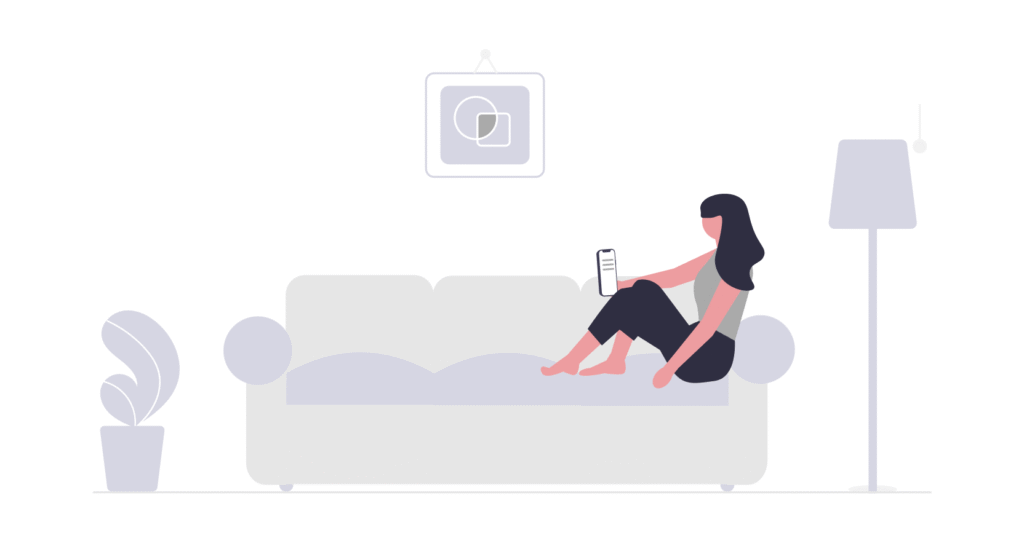
他人は関係ない。自分にフォーカス
蓄財は自分のゴールを目指して続けていくことが大事だと思います。人と比べてもお金が増えるわけじゃありませんし。自分のゴールテープだけを見つめ、走り続けるだけでOKです。
その走るペースも速くか遅くかはそれぞれのペースでいいのです。いつまでにどのくらいのゴールを目指すかを明確にすれば走るペースが決まります。
自分のペースで無理のない範囲で、継続できるようにみんなで頑張りましょう。